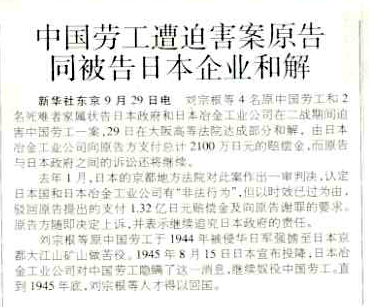- ホーム >
最新ニュース
中国人強制連行・強制労働京都大江山訴訟の和解!*中国人強制連行・強制労働京都大江山訴訟
弁護団 団長 弁 護 士 畑 中 和 夫

中国河南省、黄河北岸の新郷市郊外の農村から、強制連行され、京都府加悦町(現野田川町)の日本冶金大江山ニッケル鉱山で、強制労働に従事させられた中国人労工たちが、日本国および日本冶金工業株式会社に対して、謝罪と損害賠償を求めた訴訟である。
第一審の京都地方裁判所は、原告主張のほとんどを認めながら、時効・除斥期間の経過を理由に請求を棄却したので、原告らは直ちに大阪高等裁判所に控訴した。去る9月29日、控訴人ら(原告ら)は、裁判所の勧告に応じて、被控訴人(被告)である本件企業と和解した。和解に応じない日本国との訴訟は、なお継続中である。
訴えの提起から和解に至るまでの6年近くの間、10回近くの現地調査や聞き取り調査で、原告たちの「強制連行・強制労働の事実を認め、賠償金を支払ってほしい」という要求は終始変わらなかった。強制連行中の、さらには強制労働を強いられた期間の非人間的な取扱に対する憤りは脳裏を離れず、帰国後は「漢汗」(売国奴)と疑われ、本人はもちろん、子や孫たちまで肩身の狭い思いをさせられてきた。農村の大家族制と老人尊重の気風にまもられて、原告たちの生活はそれなりに安定しているようにみうけられた。しかし労働力としての役目を終えた老人たちは、周辺や家族に気兼ねしながら孫やひ孫たちとひっそりと余生を送っているようにみえた。この年老いた原告たちに安らぎを与えかつての威厳をとりもどしてほしいというのが、弁護団の活動の原点基本であった。
昨年12月、大阪高裁第10民事部は和解を勧告した。国はこれに応じなかったが、本件企業はこれに応じる姿勢を見せた。国も同種訴訟中の他企業もかような和解に応じようとしない中で、本件企業のみが和解に応じる姿勢をみせたことに、弁護団は訴訟の前進的解決に寄与すると判断した。
しかし両者のへだたりは遠く、何度か和解協議の打ち切りの危機に直面した。
本件企業に、強制連行・強制労働の事実をどのように認めさせるかが最大の問題点であった。結局、大阪高裁民事第10部が、控訴人ら(原告ら)の強制連行・強制労働の事実とその違法性を認定した京都地裁判決を踏まえて、審理の長期化と控訴人ら(原告ら)の高齢化にかんがみ和解を勧告し、本件企業がこれに賛同するという形をとることになったのである。企業がはっきりとはいわないが、この文脈から強制連行・強制労働の事実を認めていることは明かである。
しかしなおもう一つの大きな問題が立ちはだかった。本件企業は、この和解をもって強制労働問題の全面的解決とし、今後、同種の紛争が惹起されることはないとの理解の下に本件和解に応じるとの姿勢を崩さなかったのである。本訴以外の被害者の権利の封殺になる企業側の態度は、弁護団の憤激を呼び起こした。だがこの問題点も、本件企業が突然翻意して、同種の紛争が惹起されることはないと期待して、と譲歩してくるにおよび本訴外被害者の提訴を可能にするものと同意するにいたったのである。
和解金額も最初50万円から始まった交渉で、終局的には一人350万円に落ち着いた。
この間、本年5月3日に控訴人の一人・唐永茂さんが死去した。一審裁判中に何さんがすでに死去しており、原告の三分の一が死去したことになり、残りの控訴人も平均年齢で八〇才を遥かに超え、半分が死去してしまうのではないかと危惧せざるをえなかった。他方、本件企業もその事業報告において、リストラと中国市場の拡大により業績回復を計る方針をうちだしており、中国問題の解決が迫られていたようである。また本件企業に対して和解に応じるよう求める400以上の団体署名が集められたことも特筆さるべきであろう。こういった法廷外の諸要因が、国を動かすほどにはいたらなかったが、本件企業を和解に踏み切らせることになったのである。
しかしなお残る手続法上の問題があった、中国民訴法第59条の「訴訟代理人が・・・・和解を行い、反訴または上訴を提起するにあたっては、受託者の特別の委任がなければならない」とする規定である。和解の目途がある程度ついた段階で、弁護士2名を現地に派遣して、客観的かつ誘導にわたることなく、訴訟の現状を説明し、和解内容を解説して控訴人らの選択にまつことにした。本件訴訟において補佐人となった中国律師・康健女史も同席し、延々4〜5時間におよぶ議論を経て、全員の同意を得ることになった。さらに留意しなければならない問題もあった。中国内の各種支援団体(全華律師協会、中国人強制連行・強制労働被害労工聯誼会など)の理解を得ておくことである。
和解に同意した控訴人らが、あやまった反日感情の高揚の中で「つらい目に遭わないよう」十分な配慮をするよう依頼する作業であった。これも強制連行・強制労働の事実を明示的に確認していない点を遺憾としつつも、日本側の文脈上は事実の認識を含むという説明に理解を示し、最終的に本件和解を支持するとの回答を得ることができた。
本件和解に至る経過はおおよそ以上である。本件和解は企業との和解にすぎず、国に対する訴訟はなお全面解決を目指してねばりづよく継続する。これはまた控訴人らの意思そのものでもある。 控訴人らの意思こそ本弁護団の活動に基調であったことを強調しておきたい。