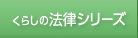Q、13歳の少年(中学生)が、高校生らの不良グループと一緒に、通りがかりの人に殴るけるの暴行を加え、怪我を負わせたことから、逮捕されてしまいました。どうなってしまうのでしょうか。
A、14歳に満たない子どもには刑罰を加えることはできません(刑法41条「14歳に満たない者の行為は、罰しない」)。
少年法でも、「罪を犯した少年」にはあたりません。
そこで、刑罰法規に触れる行為(犯罪行為)を犯した少年(「触法少年」といいます)については、児童相談所が対応することになります。
犯人が14歳未満かどうか不明の場合には、警察は通常通の捜査ができますが、犯人が14歳未満であることが判明した場合には、処罰を目的とした捜査はできませんので、警察は任意捜査の範囲で捜査を行い(嫌なら断ることもできるのです)、児童相談所に、保護が必要な少年であるとして通告します。
その後、場合によっては、都道府県知事や児童相談所長が、家庭裁判所に事件を送致することもあり、その場合には、14歳未満の少年(児童)でも家庭裁判所で審判を受けることになります。
児童相談所の措置としては、児童や保護者に注意を与え誓約書を書かせる、指導福祉司などに指導を委託する、里親などに預ける、養護施設に入れるなどもあります。
家庭裁判所での審判がなされることになった場合でも、とりわけ14歳未満の少年(児童)は、精神的にも未発達ですので、矯正教育が必要な場合であっても、基本的には児童自立支援施設に行くことになります。
ところが、この間、触法少年の重大事件が起きたのをきっかけに、少年法を改正し、14歳未満の触法少年であっても警察の捜査(強制捜査)ができるようにし、少年院にも収容できるようにしようとした動きがあり、「おおむね12歳以上」の少年は、初等少年院や医療少年院に収容されることが可能となりました。
もともと、少年法は、少年の精神的未成熟さを考慮し、非行があっても罰を与えるのではなく、福祉的な対応により、少年の更生を図ることを主眼としていますので、本来のあり方とは真っ向から反する方向です。
少年に対して、処罰を重くしたから少年非行が減少するなどということはありません。
近年、少年の重大犯罪が激増しているなどと宣伝されたりしていますが、データに基づけばそのような事実はありません。
少年犯罪については、未成熟な少年ゆえに犯してしまった深淵にある原因を探り、少年が更生するために何が最善な手段なのかを探ることが重要なのです。
年齢、発達段階など、その子ども一人一人の成熟度に応じた対応をしないと、本当の意味でその少年の立ち直りを期待することは難しいのです。