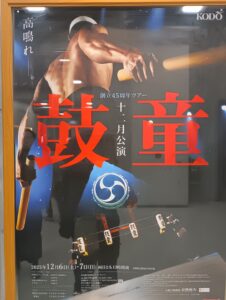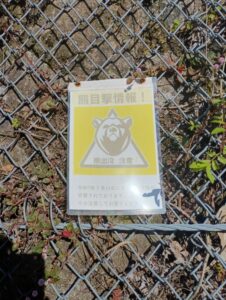2025年10月28日付け当ブログで紹介した、鈴木俊貴さんの著書「僕には鳥の言葉がわかる」を読んで以来、自分の目で「鳥を見てみたい」という思いが強くなった。
観劇用の双眼鏡しか持っていないが、さっそく昨年のある日曜、それを持って京都御苑に出掛けた。
しかし、鳥の鳴き声はあちこちから聞こえるものの、目に入るのは、カラスや雀ばかりで、それ以外の鳥は見つけられず、失意のうちに帰宅した。
そうしたところ、カルチャーセンターで「初心者のためのバードウオッチング」という講座があることを知り、場所も京都御苑だったので、すぐに申し込み参加した。
-300x226.jpg)
とても寒い日だったが、天気は良い。参加者は5名。私以外の参加者は、皆、バードウオッチング用双眼鏡を持参されていたので、どうやら純粋「初心者」は私だけのよう。
講師から「どこに鳥がいるか、自分で見つけらるようになりますよ」と言われたが、前に見つけられなかったので、本当に見つけられるだろうか?と不安を感じながら、講師の後をついていった。
まず、京都御苑の南西端にある「閑院宮家」に入る。長く京都に住み、京都御苑も何度も来ているのに、ここに入るのは初めて。
-300x226.jpg)
敷地に入ると、池があり、そこで観察が始まった。
-300x226.jpg)
「カワセミ」がいるとのこと。「カワセミ」は、冬の間は、大体、同じような場所を移動するとのこと。
講師は、まず肉眼で確認されて、その位置を教えてくれる。池の周辺に1羽だけいるとのこと。
教えられても、最初はなかなか自分の双眼鏡にその姿が現れなかったが、何度か探しまくり、とうとう、鳥の姿が目に飛び込んできた。
感動!
講師は、大きなカメラをセットしてくれて、そのレンズを除くと、背中と羽根が青色、おなかはオレンジ色をした美しい鳥がそこにいる。
これが「カワセミ」!? 美しい!
1度見つけると、どれだけ見ていても、見飽きない。場所を教えてもらいながらも、自分の目で、自分の双眼鏡で確認できるのが楽しい。
次の場所に移動。
京都御苑の木立の中。枯れ木と思われる背の高い木をジッと見上げていると、同じ種類の鳥たちが上方に何羽も止まっている。
「イカル」という鳥とのこと。講師の大きなカメラを覗くと、嘴が黄色だ。
枯れ木に何羽もとまっている。そして、枯れ木と見えたが、実は、小さな実がついており、鳥たちはそれを食べているのである。面白い!
松林の中にも、鳥はいた。
「ビンズイ」
何個も地面に落ちている松ぼっくりをよく見ていると、何やら茶色の動く物体が。
これが「ビンズイ」。
雀の歩き方はホッピングだが、「ビンズイ」は「歩いている」。茶色なので、遠くからだと松ぼっくりと見分けがつかない。
講師によると、今日だけで、15種類位の鳥を確認したとのこと。私自身は、そこまで確認はできなかった。
でも、とにかく、自分の安物の双眼鏡でも、自分の目で鳥を確認できたことは、とても感動的だったし、いつまでも見飽きないものだ。実に面白かった。
これからは、鳥にももっと興味がわいてきそうな予感。
後日談。
カルチャー終了数日後の昼休み、再度、一人で、京都御苑に行き、再び「閑院宮家」に行ってみた。
すると、大きなカメラ持参でバードウオッチングをしている男性から「さっきまで、カワセミがいたよ」と話かけられ、また、京都出身で関東に住んでいるという女性も、自分で映したという京都御苑の鳥の写真を見せてくれた。
-300x226.jpg)
なんか鳥だけでなく、人の輪も広がりそう・・・