先週放映の朝ドラ「虎に翼」では、主人公寅子(ともこ)が新潟地裁で、朝鮮人がスマートボール場を放火したという刑事事件を担当するという場面がありました。
今回の朝ドラは、朝鮮人差別の問題についても正面から取り上げています。
寅子の大学時代の友人の朝鮮人ヒャンちゃん(崔香淑=チェ・ヒャンスク)が、兄が思想犯の疑いで連行され帰国せざるを得ず司法試験をあきらめ、その後結婚して日本人として生活せざるを得ない姿が描かれています。
そして、新潟に移った寅子が担当した事件が、上記の朝鮮人の刑事事件でした。ドラマの中では、寅子がヒャンちゃんの協力も得て、検察官提出の証拠の1つである被告人の手紙の訳が誤訳であることがわかりました。
この裁判も実際にモデルとなった事件があることがわかりました。
昭和33年7月25日長野地裁飯田支部で、倉田卓次裁判官(当時)が言い渡した無罪判決です。
被告人は朝鮮人。スマートボール遊戯場を経営しており、100万円以上の負債があり、火災保険金目当てに放火したとして起訴されました。
法律雑誌である判例タイムズ82号P84~に詳細が掲載されています。
判決文を読むと、被告人には本件犯行をなすに至る動機も可能性もあるものの他の可能性への合理的な疑いを排除するだけの証拠が見いだせないと判示した無罪判決で、詳細に事実認定がされています。
ドラマの中の、手紙の誤訳の部分ですが、実際の判決でも、それに似た指摘がなされています。
それは、翻訳では左から右に読むべき朝鮮文を右から左にへ訳していることが明らかになったため検察官はその証拠を撤回したと書かれていました。
勉強になります。








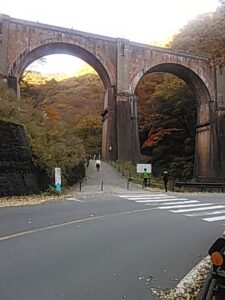


-300x169.jpg)
-225x300.jpg)
-300x225.jpg)
-225x300.jpg)
-300x225.jpg)
-225x300.jpg)
-300x225.jpg)
-225x300.jpg)
-225x300.jpg)
-300x225.jpg)
-225x300.jpg)



