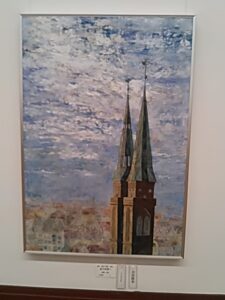2011年3月11日、あの東日本大震災が発生した日、宮城県石巻市大川小学校の児童74名は、すぐ南側に誰もが走れば1分足らずで上れる裏山があったにもかかわらず、校庭で約51分待たされた挙げ句、70名の命が失われ、4名の児童が行方不明となった。
映画「生きる」は、その事件の裁判を闘った遺族たちのドキュメンタリー映画である。
私の司法研修所時代の同期(34期)の弁護士2名(吉岡和弘弁護士・齋藤雅弘弁護士)がこの大川小学校津波裁判を担当していたという関係で、この映画のことを知った。
大川小学校津波裁判では、仙台地裁は、2016年10月26日、津波が学校に到達する7分前に教師らに津波到来の予見可能性があったと認め、遺族勝訴の判決を言い渡した。その後、仙台高裁は、2019年4月26日、石巻市、市教委、校長など指揮命令に位置する者らを「組織」でくくり、地震や津波が発生する遅くとも1年前の時点で児童らの安全を確保するための職責を果たすべき義務を怠った責任を認める判決を言い渡し、2019年10月10日、最高裁も高裁判決を維持し、判決は原告遺族勝訴で確定した。
しかし、最高裁で勝訴しても、原告遺族たちは落ち込んだという。
1つは、遺族らが求めた「なぜ子どもらが亡くならなければならなかったのか?」が裁判で明らかにならなかったこと、そして2つめに、遺族の活動に対し、様々な場所や機会、媒体によって、心ない人々から罵声や誹謗中傷が浴びせられたからだ。
原告遺族らは、金銭賠償をしてほしいために国賠訴訟を起こしたわけではなく、裁判以外に方法がない状況に追い込まれ、提訴したのだ。
2023年2月26日、吉岡弁護士の紹介で、この映画を製作した寺田和弘監督と会う機会を得た。
監督は、裁判というものを知らない遺族らが、今日まで、どのように乗り越えて来たのか=親の闘いを描くことで子どもの姿を描くことにつながること、そして、今の日本の姿を描き、あの日何があったのかがわからない限り教訓にはならないと熱く語られた。
京都では、3月10日から30日まで、京都シネマで上映されます。
是非、多くの皆さんに観ていただきたいと思います。
-225x300.jpg)






-300x225.jpg)

-225x300.jpg)
-225x300.jpg)
-300x225.jpg)
-225x300.jpg)
-225x300.jpg)
-225x300.jpg)
-225x300.jpg)








-300x225.jpg)
-300x225.jpg)
-300x225.jpg)
-225x300.jpg)
-225x300.jpg)
-300x225.jpg)