2011年3月の東北大震災の際の支援を通じて、ずっと交流が続いている宮城県気仙沼市のYさん。
お目にかかったことはないが、互いに「もう親戚以上の付き合いですね」と言い合う仲になっている。
そのYさんから、今年もサンマが届いた。
夏にこちらから荷物を送った時にいただいたYさんからの返事の中に、「サンマを送ります」と書かれてあったが、その後、今年も昨年に引き続きサンマは不漁、気仙沼のサンマまつりも中止という新聞報道を目にしたり、京都のスーパーで売られているサンマもすべて北海道産だったりするため、今年はダメかも・・・と思っていた。
それが、数日前、Yさんからサンマが届いた。
嬉しい!
例年より小ぶりのサンマだが、おいしい!
その上、今回は、サンマだけでなく、カツオが1本まるごと入っていた。

で、で、でかい!
ところが、
どうしよう・・・私は魚をさばけない・・・
そんな時、頼もしい助っ人が見つかった。
それも若くイケメンのM弁護士(でも、もう立派な中堅弁護士です)。
なんでも小さい時から両親に教えられて、魚をさばけるとか(偉い親やね)。
「カツオはうろこがないから、おろしやすいんですよ」と言いつつ、
「こんなデカいカツオは、切ったことがないなあ」と頭の骨を切る時は、かなり力を入れてさばいていた。
でも、見事! 30分もかからず解体完了。
さすがの腕前!
その日の夕食は、もちろん新鮮なカツオの刺身。
美味でした。
Yさん、本当に有り難うございました。
ブログ マチベンの日々
国連総会では、北朝鮮に対し各国から厳しい批判が相次いだが、北朝鮮への対応をめぐる各国の指導者の発言内容はかくも違う。
2017年9月22日付け京都新聞朝刊は、「危機的な状況にあるとはいえ、あざけりや対立をあおるのが『偉大な国』の指導者にふさわしいとは思えない」と論評した。
米国トランプ大統領は、就任後初めて国連総会の一般討論で演説を行った。
北朝鮮の金正恩委員長を「ロケットマン」とあざけり、「自国と同盟国が防衛を迫られれば完全に破壊するしか選択肢はなくなる」と警告した。
北朝鮮も挑発的な言葉を発し続けているが、トランプ氏も同じレベルとしか思われない。
安倍首相も、トランプ氏に呼応し、「(核計画放棄のために)必要なのは対話ではない。圧力だ」「『全ての選択肢はテーブルの上にある』とする米国の立場を一貫して支持する」と述べた。
他方、ドイツのメルケル首相は、ドイツの海外向け公共放送のインタビューで次のような発言を行った。
トランプ氏の発言に対し「このような脅しには反対する」と明言し、「ドイツ政府はどのような武力解決もまったく不適切だと判断するし、外交努力と(国連安保理決議の)制裁実現が正しい答えだ」と強調した。
更に、「(北朝鮮をめぐる)紛争はドイツにとっては空間的には遠いがそれでも打撃になる」と懸念を表明し、「だからこそ、われわれは北朝鮮の紛争の平和的解決にまい進する用意がある」とした。
フランスのマクロン大統領も、米CNNへのインタビューで「軍事的解決を選択すれば、多くの犠牲者を生むことになる。私は多国間による交渉を通じて、平和を構築できると信じている」「緊張を緩和し、周辺地域の国民を保護するための適切な答えを探すことが私たちのすべきことだ」と語った。
安倍首相は、国連総会では「脅威はかつてなく重大で、眼前に差し迫ったものだ」と強調しながら、国内では、原発を停止することもなく、衆議院解散によって政治的空白を作ろうとしている。
結局、国民に不安や危機感をあおっているだけにすぎない。
9月17日(日)、台風が西日本を通過する予定だったが、朝から夕方までは、曇り空のまま、雨は降っていなかった。
そこで、思い立って、三条会商店街の中にあるカフェの「10分モンブラン」を食べに行ってきた。
「10分モンブラン」のことは、今年4月にテレビ朝日「LIFE~夢のカタチ~」で放映されて知った。
三条商店街にある「Sweets Cafe KYOTO KEIZO」のオーナーパティシエ西田敬三さんは、他店で洋菓子職人として40年勤め上げ、還暦を迎えてから独立した。
そして、オープン時に目玉として売り出した賞味期限10分という「10分モンブラン」は、そのネーミングも手伝って、大評判となった。
三条会商店街は、それほど遠くないので、食べてみたいと思ったが、行列してまではね・・・
そこで、台風が来そうな日なら、観光客も来ないだろうし、そんなに混んでいないと予想し、9月17日、少しのRUNとあとは歩いて三条会商店街へ行ってみた。
三条会商店街は、堀川通りから千本通りまでの三条通にあるが、店は堀川通りに近かった。
店に着くと、家族連れが1組だけ待っていただけで、すぐに入店できた。
10分モンブランを食べに行ったのだが、店員さんから、季節・期間限定のビスタッチオのモンブランがあると聞いて、それを注文した。
私の順番が回ってくると、店員さんから「作っているところを見ていただけますよ」と声がかかったので、奥の工房を覗かせてもらった。
西田さんが作っている!


3個ずつ、アッという速さでできあがっていく。
いよいよ、テーブルに運ばれてきた。
見た目は普通のモンブラン。

また店員さんが、詳しく説明してくれる。
「5分、10分経つと、食感が変わりますよ」と。
中はこんな風になっている。

中に、メレンゲの固まりが入っていて、それが最初はサクサクで、時間の経過とともに、溶けていってクリーム状になる「構造」のよう。
納得。
でも、食べ終わるまで10分も持たなかったよ。
おいしかった!満足!
9月7日発売の週刊文春を購入した。
別に、山尾志桜里衆議院議員の不倫疑惑記事が読みたかったわけではない。
めったに買わない週刊誌を買ったのは、「楠木新氏が教える『定年後』に輝くための7カ条」という記事が読みたかったからだ。
実は、楠木新氏(注、ペンネームです)は、大学の時のクラスメートである。
大学卒業後は全く交流がなかったが、数年前から毎年開催されているクラス会で再会し、50歳の頃から会社に勤務しながら、「楠木新」という名前で執筆活動をされていることを知った。
「人事部は見ている」(日経プレミアムシリーズ)とか「働かないオジサンの給料はなぜ高いのか」(新潮新書)など、結構、その著書は人気がある。
最近出版された「定年後」(中公新書)という本は、発行部数が20万部を超えたとのこと。
先日、書店に行ったら、この本が平積みしてあったので、やはり人気があると確信した。
今回の週刊文春の記事では、数多くの定年退職者や、中高年以降に会社員から異なる仕事に転身した人たちの取材から、定年後をイキイキと過ごすための行動のヒントが7カ条にまとめられている。
以下は、その要約。
第1条 退職3年前には準備を始める
自分の立場を変える、それまでの世界とは違う「面白いこと」を身に着けるのには、3年程度の時間が求められる。
より早くスタートする方がスムースに進み、選択の幅が広がる。
第2条 お金がもらえる趣味を探す
収入があるということは、誰かの役に立っていることであり、社会的なつながりを持つ活動になる。
また、自分の力量をアップすることにもつながる。
第3条 同窓会で子ども時代の自分を発見
子どもの頃と今がつながっている。
第4条 若い頃は趣味より仕事
40歳位までは懸命に仕事をした人の方が、その後の仕事の選択の幅が広がる。
働いている組織をよく知るためには、一度は仕事にどっぷりとつかった方が良い。
第5条 個人事業主に学ぶ
個人事業主は社会と直接的につながっている。
個人事業主に接触すると、会社員の自分を客観化することができる。
第6条 ロールモデルを探す
会社員から転身した人で、こうなりたいと自分が思う人に近寄り、時間と空間を共有しながら、その人と自分を重ね合わせてみる。
個性も経歴も異なったとしても、自分の歩む道も見えやすくなる。
第7条 自分を変えるのはムリ
自分自身を変えるのは難しい。自分を変えようとするよりも、ありのままの自分をどこに持っていけばよいのかを検討する方がうまくいく。
番 外 挫折や不遇体験は役に立つ
自分の悩みに関わることや、そこから派生することがきっかけで一歩前に踏み出す人が多い。
ここで大切なことは、悩みや挫折から目をそむけないこと。
楠木氏は、60歳の定年後から、他人の支援や介助を受けなくてすむ75歳くらいまでの期間を「黄金の15年」と名付けて、ここが人生後半戦の勝負所だとする。
そして、また、楠木氏は、最後に「顔つきがポイント」と言う。
「発言では美辞麗句を並べることはできても、顔つきだけはごまかせない」「その人の内面の状況をあらわすのは顔つきであるからだ」と。
「自分にとって本当に大事なものや、自分が果たすべき役割に気づいた人は、優しいまなざしをもった穏やかな表情になる」
「定年後は『いい顔』になることに取り組んでみればいいわけだ」と結ぶ。
私たち弁護士は、多くは、上記の個人事業主であり、定年はない。
それがいいか悪いか・・・
なぜかというと、「黄金の15年」をどう生きるのかを考えることなく、これまでと同じようにダラダラと人生を過ごしてしまう「恐れ」もあるからだ。
今のままでいいのか、と常に自問自答している。
最近は、大学のクラスには参加できていない。
来年は参加して、楠木氏と話をしてみたいと思った。
●8月4日 烏帽子岳(2628M)、8月5日 野口五郎岳(2924M)
烏帽子岳から野口五郎岳へという裏銀座縦走コース。
ちなみに、歌手の野口五郎は、この野口五郎岳から芸名を取ったとのこと。
私は、1999年8月にこのコースを歩いたことがあり、今回は18年ぶりに同じコースをたどった。
前夜は、七倉山荘に宿泊。18年前にも宿泊した七倉山荘は、当時は、山小屋と民宿の中間のような雰囲気だったが、とても綺麗に改装され、部屋(個室)にはテレビもあり、浴場には露天風呂もあってまるでホテルのような浴室だった。食事もとてもおいしかった。
朝一番(午前5時半)に東京電力のゲートが開くのと同時にタクシーに乗って、高瀬ダムまで。ここからは、徒歩で行くか、タクシーでしか入れない。
高瀬ダムは、岩を積み重ねたロックフィルダムで堤高は176m、黒部ダムに次いで日本2位の高さ。
ダムの最上部でダクシーを下りる。

トンネルからスタートし、長い吊り橋を渡り沢を渡ると、ブナ立て登山口。
登山口の手前にある沢は、普段は小さな沢だが、雨が降ると、山の上から土石流が流れることがあり、1998年夏には、大学生二人がこの沢で流され、一人が死亡した。
私が前に登った1999年には、亡くなった女子大生の碑があったが、今回、その碑は見あたらなかった。

ブナ立て登山口。
高瀬ダムから烏帽子岳までの登山道は、ブナ立て尾根と呼ばれ、北アルプスの三大急登の1つと言われている。
この登山口から烏帽子小屋の付近までの登山道には、⑫から①までの番号がついた標識が立てられており、目安となる。

三大急登とは言うもののストックが使える程度であるが、この日は、気温が高く風もなく、蒸し暑く、苦しい登りであった。
でも、高山植物もたくさん咲いている。


④は三角点。もうバテバテである。

何度も休みながら、やっと烏帽子小屋に到着。
周囲の山々にはガスがかかって、あまり見えない。
それでも、小屋の前には、たくさんのイワギキョウが群生しており、疲れを癒してくれた。

小屋の前で30分ほど休憩を取った後、烏帽子岳に向かう。
烏帽子岳

烏帽子岳の頂上直下は、かなり急な岩場で、怖かった。
「怖い」という記憶があまりなかったということは、18年前は、軽々登れたのかな・・・・
狭い頂上に立ったものの、ガスで何も見えず、人もたくさんいたので、早々に下山。
小屋に戻る途中、雷鳥と出会う。

翌朝は、午前5時15分に出発し、野口五郎岳に向かう。
起床した時には晴れていたが、すぐにガスが上がってきた。
途中一瞬、槍ヶ岳が見えたが、その後は、ひたすらガスの中を歩く。
野口五郎岳もガスの中。

写真だけを撮って、先に進み、分岐から湯俣温泉方面に竹村新道を下山した。
ただ、これがまた、かなりザレた登山道のハードな下りで、湯俣温泉に着いた頃には、もうヘロヘロになった。
この裏銀座縦走コースは、表銀座コースと異なり、登山者もそれほど多くなく、しかも晴れていれば、すっと槍ヶ岳を眺めながら歩くことができる絶景の快適コースである。
今回は、全くその醍醐味を味わうことができなかったことが、つくづく残念。
もうすぐ8月も終わろうとしており、今年もいくつかの夏山に登った。
しかし、今年は、2017年7月25日付けブログで書いた北海道を始め、どこの山に登っても天候不良で、自分が本当に「雨女」かもしれないと思ってしまう。
田部井淳子さんをはじめ、著名な登山家たちは、その著書などで「雨の日の登山も楽しい」と書かれているが、周囲の山々が何も見えない中を黙々と歩いていくのは、正直つらかった。
●7月23日 仙丈ヶ岳(標高3033M)
仙丈ヶ岳は、南アルプスの山で、日本百名山の1つ。
私は2013年7月に日本百名山を完登したが、100座の山を登ったうち、雨の中を登った山もいくつかあり、仙丈ヶ岳もその1つであった。
仙丈ヶ岳は、花の百名山でもあるので、是非、高山植物が咲く頃に登ってみたかった。
当初の天気予報では晴予報であったが、直前に天候悪化となった。
前夜、北沢峠のこもれび荘(綺麗に改装されていた)に泊まり、翌朝午前5時15分出発。
天候は曇りで、周囲の山々はガスで見えない。
沢沿いの登山道を登る。沢にはまだ所々雪渓が残っていた。

高山植物もたくさん咲いている。
ウサギギク

 キバナシャクナゲ
キバナシャクナゲ
沢から離れ、樹林帯の登山道を少し登ると、馬の背ヒュッテという山小屋が現れた。
しかし、この辺りから雨が降り出す。
馬の背ヒュッテから尾根を歩き、急坂を登って仙丈小屋に到着。
小屋の自炊室で昼食を食べていると、少しだけガスが切れ、仙丈ヶ岳の頂上が見える。
昼食後、登頂。

ガスが取れることを期待して約20分ほど頂上にいたが、結局ガスは取れず、泣く泣く下山した。
2017年8月22日付け京都新聞朝刊「こころに社会を刻む」という特集記事で、第2次世界大戦末期、京都が原爆の投下目標の最優先標的としてリストアップされていたことを取り上げていた。
記事によると、京都が原爆投下目標となった経過は、次のとおりだ。
●1945年4月27日 原爆の「標的委員会」初会合。優先順位①広島②京都③横浜。
標的選定については、①日本に最大限の心理的効果を与えること、②公表時、世界中にこの兵器の重要性を認識させるため、最初の使用は壮大なスペクタルになるようにすること。
そして、「知的水準の高い人がいる京都は兵器の意義をわからせる上で優位だ」と報告された。
●同年5月10・11日 第2回「標的委員会」。原爆投下の第1目標を京都に。以下、広島、横浜、小倉、新潟。
●同年5月28日 第3回「標的委員会」。原爆の標的都市は通常の爆弾で空爆せず、「保全」するよう空軍に要請することが決定される。
●同年5月29日 横浜は標的リストから外れたため、この日、横浜大空襲。
●同年7月16日 米ニューメキシコ州で初の原子爆弾の爆発実験に成功
●同年7月25日 広島・小倉・新潟・長崎を標的とする原爆投下指令
京都は、最初の投下目標から外れ、8月中旬の3発目の原爆投下の対象として想定。
●同年8月2日 米空軍、①広島②小倉③長崎に6日投下を発令
●同年8月6日 広島に原爆投下
●同年8月9日 小倉が視界不良のため、長崎に原爆投下
●同年8月15日 日本が降伏
標的の選考は、地形や建物の分布は爆風の効果を測定しやすいかや、心理的ダメージの大きさが重要項目で、文化財はまったく考慮されていない。
京都の爆心地は、京都市下京区の梅小路機関車区(現在の梅小路公園)に設定されていた。
京都は最後まで標的から解除されなかったのであった。
京都と同じく投下目標だった小倉(現在の北九州市)では、市が平和資料館建設の整備計画を進めている。米軍が原爆を落とそうとした歴史も展示する予定だ。2010年には非核都市宣言も出している。
もし、戦争がもう少しだけ長引いていたら、京都にも原爆が投下された可能性は非常に高い。
その意味で、京都の自治体は、被爆の准当事者として、もっと核兵器禁止の問題や平和の問題に取り組んでいかなければならないと強く思う。
8月16日、京都五山の送り火の夜。
「今年は雨が降らなくて良かったね」(昨年、大雨でした)と言いながらも、送り火を見ることはなく、食事に出かけた。
京都の路地裏のレストラン「ORTO」(オルト)(衣棚通三条下る)。
2017年8月5日放映のテレビ朝日の番組「LIFE~夢のカタチ」では、「ORTO」のオーナーシェフ谷村真司さんが登場した。
「ORTO」はイタリア語で「菜園」という意味。
京都府久御山町の実家で取れた野菜やハーブをふんだんに使って、一皿一皿の料理を、まるで絵画のように作り上げる。
場所も近いので、行ってみたいと思った。
普通、テレビで放映されると、しばらくは予約が取れないものだが、16日は送り火を見に行く人が多いせいだろうか、思いがけず、予約を取ることができた。
店は、細い路地裏にあった。
1階はカウンター席で、2階はテーブル席。
夜は、コース料理のみ。
メニューには、メインの素材の名前しかかかれていない。
まずは、「前菜」
豚肉を使った揚げものとフルーツソース。

「茗荷」(みょうが)
黄色の茗荷の花の下には、しまあじのお造り。それを右横のシャーベットで混ぜながらいただく。

「鮎」
川のようなイメージで描かれているのは、バジルソース。

「茶そば」
茶そば・おくら・きゅうり・たこが混ぜ込んである。

「菜園」
もしかしたら、この料理がORTOの本当のメインかもしれない。
実に40種類以上の野菜とハーブと花が使われているサラダ。

「鰻」(うなぎ)
鰻になすが沿えてあり、上にはなすの皮も乗っている。

「雲丹」(うに)
「箸休めです」と。エッ!箸休めに雲丹!!雲丹の下には、もずく酢とクリーム

「夏鹿」
初めて鹿肉を食べた。赤身肉で食べやすい。

「キーマカレー」
メニューには載っていないが、シェフが作ったスパイスと鹿肉を使ったカレー。

「西瓜」(すいか)
デザートの1番目は、西瓜とシャーベット。

「無花果」(いちじく)
デザートの2番目。

どの料理もとてもおいしく、1皿の量は少な目だが、おなかは一杯になった。
久しぶりに優雅な夕食となった。
また季節を変えて、訪れてみたい。
7月の連休、今年最初の夏山登山に出かけた。
行き先は北海道の大雪山系。赤岳から緑岳への縦走登山。
梅雨も明けないまま、日本各地でゲリラ豪雨があったり、北海道帯広では連日37度の猛暑日が続いたりと、天候や気象はとても不安定。
初日は、札幌から旭川までJRで行き、旭川駅前から層雲峡まで向かう予定だった。
ところが、旭川付近が大雨のため、JRは運休に。
急遽、高速バスで旭川に向かうことになった。
2日目、この日がメインの縦走日。曇ってはいたが、雨はまだ降っていない。
朝6時に層雲峡発のバスで銀泉台まで。
バスの終点から林道を15分ほど歩くと赤岳登山口がある。
天気は曇りだが、まだ雨は降っていない。

少しの間、急坂を登って行くと、目の前が開け、そこに雪渓が横たわっていた。
第1花園と呼ばれる場所だが、花は咲いておらず、一面の雪渓。

第2花園も雪渓

ここ数日の北海道の猛暑で、雪渓もずいぶん緩み、アイゼンがなくても、ストックを使って慎重に歩を進めれば、なんとかトラバースすることができた。
雪渓の超えると、コマクサ平へ。

コマクサは、花の形が馬(駒)に似ていることから名付けられた。


」
コマクサ以外にも色んな花が咲いている。
チングルマ

コマクサ平から赤岳までは、第3雪渓と第4雪渓という2つの大きな雪渓の急斜面を上り、赤岳に到着。
第4雪渓直前から小雨が降りだしたため、赤岳(2078M)の山頂の写真は撮取り忘れてしまった。
そこから、ほぼ平行移動で、小泉岳へ。

小泉岳は、どこが山頂かわからない平坦な山。
標識だけが手がかり。
雨が強くなってきたため、白雲岳避難小屋で雨やどりしながら昼食をとることにして、ちょっと寄り道をする。
ここの小屋は、以前、旭岳からトムラウシ山まで縦走した時に、宿泊した小屋だ。
昼食後は、緑岳への登山ルートに戻る。
緑岳山頂。

緑岳からは、雨もようやくやんだが、ガスがかかり、ほとんど周囲の山々や景色を見ることはできなかった。
岩場を下り、その後は背丈より高いブッシュの中の登山道を進み、雪渓をいくつも超えて、ようやく目的の大雪高原山荘に到着した。
あいにくの天候ではあったが、北海道の縦走登山は、広大な大自然の中を歩くことができ、十分楽しむことができた。
映画「スノーデン」。
劇場での公開は終了していたが、京都映画センターにより、7月13日にだけ同志社大学寒梅館で上映されたので、夜の部を観に行って来た。
7月4日のブログで書いたように、「スノーデン 日本への警告」を読んだばかりだったので、コンピューターには全く疎い私にも少しは理解でき、また、スノーデンの恋人との生活も描かれ、娯楽作品としても、とても面白かった。
実話にもとづいているのだから、結果はわかっているのに、とにかく最初から最後までハラハラドキドキ。
息を詰めて見入った。
SNSから入手した世界中の情報の中から相手の弱みを見つけだし、それを操作して有利に展開させていく手法や、敵の位置情報を知りピンポイントで爆撃する手法など、リアルなだけに恐ろしかった。
映画は事実にもとづくフィクションで、スノーデンの経歴や監視実態やそれを暴露する動機、リークの方法などがよく描かれていた。
映画ではルービックキューブが使われていたが、実際には、スノーデン氏は、大量のデータをどのような方法で持ち出したのだろうか。
実際は、香港からロシアまで、どうやって亡命したのだろうか。
興味はつきない。
9月23日には、香港でスノーデン氏が暴露した現場にいたローラ・ポイトラス氏が監督したドキュメンタリー映画「シチズンフォー~スノーデンの暴露」が上映されるらしい。
是非、こちらも観てみたい。
例えば、あなたは、5年前の今日7月4日に、自分がどこにいて何をしていたかを覚えているだろうか?そんな人は、ほとんどいないと思う。
だが、政府のデータには、それらがはっきり記録されているとしたら・・・
携帯電話やインターネットなどSNSによって、私たちの日常生活は、10年前には考えられないほど便利になった。
しかし、携帯電話は、自分がいつどこにいるかの位置情報を作り出し、誰と通話し、誰とメールしたかは、永遠に消えない記録として残る。
またパソコンやスマホの検索ボックスに入力した単語の検索記録も永遠に残る。
私たちが何に興味関心を持ち、どの政党を支持しているか、どの宗教を信じているかなどは、すべて把握されている。
私たちは、今、こんな社会に生きている。
「スノーデン 日本への警告」(エドワード・スノーデンほか著)(集英社新書)を読んだ。
エドワード・スノーデン氏は、アメリカのCIA(アメリカ中央情報局)やNSA(国家安全保障局)に所属して「スパイ」活動に従事していたが、2013年6月、アメリカ政府による情報の無差別監視をリークし、ロシアに亡命した。
当時、ドイツのメルケル首相の携帯電話まで狙われていたとあって世界は騒然となった。
この本は、昨年6月に東京大学で行われたシンポジュウムにロシアから映像で参加したスノーデン氏の話をまとめたもので、内容は衝撃的である。
アメリカ政府は、グーグル、フェイスブック、ヤフーといったインターネットサービスや通信事業者の協力を得て、電話、メール、位置情報、検索履歴などすべての情報通信にアクセスしてきたという。
治安や犯罪に無関係のすべての国内外の市民が対象とされ、その日常が、大量かつ無差別に傍受されている(それを「メタデータ」という)。
では、日本はどうか?
日本では強力な監視技術が秘密裏に日常的に用いられている。
警察が組織ぐるみで隠蔽してGPS捜査を行っていたことがその一例だ。
スノーデン氏は語る。
ハワイでNSAの仕事をしていた時、特定の調査対象の通信をすべて把握することができるツール(Xキースコア)を用いていたが、NSAが保管する通信の中には、日本のアドレスのものも多数あった。日米政府が情報交換していたことは十分にありうる。
次に、「テロの脅威」があるのだから、国民が監視されてもやむを得ないのでないか、という議論がある。
正に、先日成立した共謀罪法案について、政府は「テロ防止のため」と声高に叫んでいたし、テロ防止のためなら監視されてもやむを得ないという新聞投稿も目にした。
スノーデン氏は、日本においてテロの脅威が本当にあるのか?と疑問を呈する。
日本においては、テロは日常の脅威として存在していない。
実際の脅威の程度がどれくらいかを検証する必要があるとした上で、日本では、テロリストに殺される確率よりも風呂場で滑って死ぬ確率(厚生労働省人口動態統計)の方がはるかに高いと断言する。
また、普通の人々は、危険な活動に関与していないから監視されても問題ないのか?
アメリカのある官僚は「隠すことがなければ恐れる必要はありません」と述べて監視を正当化するという。
しかし、スノーデン氏は、プライバシーとは、悪いことを隠すということではないと断じる。
プライバシーとは自分が自分であるために必要な権利である。
思索する時、文章を書く時、物語を想像する時に、他人の判断や偏見から自らを守る権利である。
自分とは誰で、どのような人間になりたいのか、このことを誰に伝えるかを決めることができる権利である。
更に、スノーデン氏は、2013年に行ったリークが投げかけたテーマは、「監視」だけでなく、問われているのは民主主義の問題だとする。
リークは、そもそも民主主義社会で生きる市民が、十分な情報に基づいて意思決定を行えるようにすることが目的であった。
例えば、加計学園問題で、前川元文部科学省事務次官が「文書があった」と発言しようとした際、なぜか巨大メディアである読売新聞は一面トップで、彼の「出会い系バー」の記事を掲載した。
前川氏のその情報は、どこから出たのか。
そして、現職文科省職員までもが「文書はあった」と言うまでは、菅官房長官は、文書を「怪文書」と決めつけ、また前川氏の人格を否定し、そのような人物の発言などは信用できないとした。
公平公正であるべき政治が、総理のお友達を有利に扱うべくゆがめられているにもかかわらず、私たち国民は監視社会の情報操作によって、正当な判断ができなくされているのである。
では、このような監視社会に対し、私たちはどうしたら良いのか。
スノーデン氏は、メディアも市民も、政府への監視を強める必要を強調する。
結局、過剰な秘密主義を民主的にコントロールできるのは、主権者である国民なのだ。
警察によって秘密裏に行われていたGPS捜査を社会にあぶり出した訴訟のように、権力による違法な情報収集を追求する取り組みが重要であることを再認識した。
片岡鶴太郎著の「50代から本気で遊べば人生は愉しくなる」(SB新書)。
本屋でたまたま見つけた。
元々、鶴ちゃんの絵は好きで、個展は何度か見に行ったことがある。
その鶴ちゃんが、今度はヨガ?最近、ネットで、ヨガのインド政府公認のインストラクターの認定を受けたという記事を読んだばかりで、なんでも「極める」人だなあと思っていたところだったので、読んでみることにした。
彼は、62歳だが、毎朝、起きるのが楽しみでしょうがないと言う。
「その時どきの境遇に安住することなく、新しいことにチャレンジしてきた結果、62歳になる今も、『毎朝、起きるのが楽しみだ』と断言できる人生を歩むことができているのです」。
彼が、芸人としても、役者としても、ボクサーとしても、画家としても、そしてヨーガでも成功したのは、常に自分の人生に甘んずることなく、「自分の魂を喜ばせるために」、新しいことにチャレンジしていく精神力にあったことがわかる。
本を読み進んで行くと、その萌芽は、既に中学生の頃からあった。
中学生時代、密かに芸能界入りを考えていたため、勉強はせず、試験の成績はビリかビリから2番目。
ところが、それでは、高校受験で都立高校には進学できないと知った彼は、自分で小6の教科書やドリルまで遡って勉強してステップアップしていき、わずか1ヶ月でいきなり学年トップクラスに躍り出た。
「自分はやればできるんだ」という自信。
彼はこの時の経験を「私の人生を下支えしている出来事」と語る。
ボクシングも絵も、ストイックなまでに自分を律していく姿勢・・・
何とかして1度手をつけたものから離れずに自分の中で判定勝ちするまで踏ん張る
そうやって鍛えてきた
現状を突破しないと先に進めない
このことは前記の「高校受験のときの経験から学んだ」と語る。
「自分の魂が歓喜する『シード(種)』は、自分の中に必ずあって、自分にしか気づくことはできません」と彼は言う。
私にもそんなシードが見つかればいいなあ・・・
卵かけご飯は、最近は、たま~にしか食べない。
でも、高校生の頃は、朝6時頃に起きて、7時前後のバスに乗って通学していたので、朝起きても余り食欲がなく、毎朝、卵かけご飯を口の中にかけこんでいた。
そんな卵かけご飯であるが、テレビで「究極の卵かけご飯」というのが紹介されていた。
それは、卵の白身と黄身を分けて、まず白身をご飯と混ぜてかき回し、白身がフワフワになったご飯の上に黄身を乗せてしょうゆをかける。これなら黄身のドロッとした部分を味わいながら食べることができる。
確かに、おいしい。
白身ご飯だけを食べたり、黄身ご飯を食べたり、それを混ぜ合わせたりと、1つの卵かけご飯だが、色んな味を1度に楽しむことができる。
そして、それに加えて、「燻製しょうゆ」だ。
書店で「コスパ飯」(新潮新書)という本をたまたま見つけた。
日本マイクロソフト社の社長だった成毛眞(なるけ まこと)氏が自身が食べ歩いた料理や食材について、「うまさ」は前提条件とし、その上で、どれだけ投資効率が良いか、つまりコスパを追求した物を紹介した本だ。
その中に「特性醤油を味わう『卵かけご飯』」という項があった。
成毛氏は、卵かけご飯は、日本人にとって最高の、家で楽しむファーストフードだと言う。
全く同感。
そして彼が卵かけご飯に使う醤油が「燻製しょうゆ」だ。
赤坂にある「燻」というなかなか予約が取れない店の醤油だが、醤油自体は、品川駅構内などにある「煙事」という店舗でも販売していると書かれてあった。
食べたい。でも東京に行く機会はない。
京都のどこかの店に置いていないだろうかと探していたところ、伊勢丹のデパ地下で見つけた。
これが実に値段が高い。
通常のボトルだと、200ミリリットルで2060円だ。
成毛氏は「買って損はない」と書いていたが・・・
ところが、小さいボトルも一緒に並べてあった。
30ミリリットルで820円。しかも、スポイト付き。
これを買った。

早速、ご飯を炊いて、卵かけご飯を作る。もちろん、究極の卵かけご飯の作り方でだ。
そして、最後に、燻製しょうゆを、とりあえず数滴垂らして食べてみる。
「ああ、本当に、燻製の味や」
数滴では足りず、もう少しかけてみる。
おいしい!
実は、成毛氏は、この本で、更に続けて「ここで、燻製オリーブオイルを加えようとかは考えてはならない。そうしたらもっとうまいに決まっている。しかし、その世界に足を踏み入れてしまうのは、人として許されないような気がする。もう、あちらの世界から戻ってこれないかもしれない」と書いている。
あちらの世界から戻ってこれなくてもいい。
次は、燻製オリーブオイルもかけてみよう。
これは、今朝の京都新聞朝刊に掲載された佐藤卓己京都大学教授の「論考2017」の見出しである。
「ミサイル発射。ミサイル発射。北朝鮮からミサイルが発射された模様です。頑丈な建物や地下に避難してください」・・・だが、大地震などに比べると、その対応策はリアリティーに乏しい。
そんな書き出しから、この論考は始まる。
私も、いつぞや、北朝鮮がミサイルを発射した際のテレビニュースで、上記のようなアナウンスを耳にした。
確かに、内閣官房の「国民保護ポータルサイト」にもそのような文が書かれてある。
でも、違和感を覚えた。
外に出ても、誰も不安がったり、もしミサイルが飛んで来たらどこに避難しようというような会話すら聞かれない。
第一、北朝鮮のミサイルというのは、建物や地下に避難すれば助かる程度の威力しかないのだろうか・・・
以前から気になっていたのは、安保関連法案などの戦争法や自衛隊の海外派兵などが国会などで取り上げられるのを軌を一にしたように、テレビニュースやワイドショーなどで北朝鮮ミサイル報道がなされることだ。
まるで、日本も軍隊を持たなければ国を守れないかのごとく、国民を煽っているような気がしてならない。
佐藤教授によると、北朝鮮と戦争になれば、より深刻な事態に陥る隣国の中国や韓国では、これほどの過熱したミサイル報道は見られないという。
そもそも北朝鮮にとって、核兵器も弾道ミサイルも、使ったら最後、自らの体制崩壊を招く「終末兵器」であるので、これらは対外的には「顕示的(ひけらかし)兵器」であり、対内的には「心理戦兵器」でもある。
日本メディアの過熱報道は、北朝鮮の国策プロパガンダに無料で放送枠を提供しているに等しい。
それに対抗するには、まず相手の期待通りには映像を流さないことが重要であるにもかかわらず、映像を垂れ流す日本メディアの意図は何か。
佐藤教授は、北朝鮮の脅威は、安倍政権が進める安全保障政策の追い風となると見越して、あえて日本政府との「共犯関係」を維持しているという見立てをされている。・・・納得!
しかし、更に、佐藤教授は、「警報」の訓練の前に必要なのは、情報の意図を見抜くわれわれ受け手のリテラシーの向上だと結ばれている。
テレビや新聞だけでなく、SNSの発達によって、世の中には様々な情報があふれている。
どういう意図で情報が流されているのか、何が真実なのか、しっかり見抜くリテラシーを身につけるよう、私たちは日々努力する必要がある。
6月11日が高校の同窓会だったので、前日10日、久しぶりに郷里の岐阜へ出かけた。
前日に行ったのは、小学校時代の恩師T先生と会うため。
T先生は、小学校時代、担任ではなかったが、好きな先生の一人だった。
小学校卒業後は、年賀状を交換するだけだったが、T先生は、退職後の64歳の時、京都造形大学の学生として陶芸の勉強に京都に来られ、そのことを取り上げた記事を新聞で読んだことをきっかけに、小学校卒業以来初めてお目にかかり、以来、交流が続いていた。
今年2月、T先生からお手紙をいただき、87歳であること、3年前に心筋梗塞で入院されたり腸捻転の手術をされたこと、そして昨年、悪性の癌が発見され、2回も手術を受けられたことなどを知った。
早く会いに行きたいと思いつつ、ズルズルと時間だけが経過し、やっと6月10日再会の運びとなった。
T先生は、想像していたよりはお元気そうで、その日も、所属されている団体の会合に出席されていたとのことだった。
奥様も病気なので、T先生が食事などは作られているようで、知らなければ、そんな重篤な病を抱えておられるようには見えない。
「自分が老老介護となるとは思ってもみなかった」と言われたが、二人の子どもさんが、岐阜や愛知におられると聞いて安心した。
互いの近況や京都の話、小学校時代の話などで、話題はつきなかった。
1日も長く元気でいてほしい、また米寿のお祝いもしたい、そんな思いで別れた。
2015年5月28日付けブログで「ピースサインと平和運動の歩み」について書いた。
その際、引用した京都新聞の記事により、第2次世界大戦中、反ナチスの象徴として勝利のビクトリーを意味するVサインが欧州で広まり、これを60年代後半のアメリカで平和の象徴としての「ピース」に変え、日本に伝わったことを紹介した。
私も写真を撮られる時には、ほとんどいつもVサイン(ピースサイン)を出してしまう。
でも、今、このVサインに「待った!」がかかっている。
それが、2017年6月7日付け京都新聞夕刊の記事。
それは、インターネットに「Vサイン」をした写真を掲載すると、「指紋が盗まれる」かもしれない、という驚くべき内容。
デジタルカメラなどの進歩で、指の写真から指紋を読み取ることができるようになったためだ。
最近、オフィスへの入退室やコンピューターの利用許可などさまざまな用途のために、本人確認をする生体認証として、指紋はよく使われる情報である。
しかし、その指紋がデジカメで撮影された写真から読み取られてしまう。
確かに、デジカメで遠目に撮影された写真でも、拡大すると、顔のシワがくっきりと見えてしまうことからも、さもありなん。
盗んだ指紋を悪用した成り済ましが出てくると、深刻な事態につながりかねない。
これに対し、国立情報学研究所のチームは、盗難を防ぐ方法の開発を進めており、「1,2年後には実用化したい」としている。
Vサインにこんな落とし穴があったなんて、ビックリ!
6月4日は、虫歯予防デー。
友人Iさんが、私がブログで「歯周病になった」と書いたのを読んで、「是非、使ってみて」と勧めてくれたのが、ジェットウオッシャーと呼ばれる口の中の洗浄器。
水のジェット噴射で掃除をする機械があるが、あれのミニ版みたいなもの。
Iさんは、もう20年以上前から使用しているようで、歯はとても健康で、手放せないとのことだった。
そんな物があるとは知らなかった。
早速、ヨドバシまで行ってみた。いくつかの会社から製品が出ている。
色んな人のブログを読んで、パナソニックのドルツの新製品を買おうと決めていた。
ところが、値段が1万円以上もする。躊躇・・・
帰宅してネット(楽天)で探す。
約8000円で楽天ポイントが1000点つくのがあったので、ネットで購入することに決めた。
先週から早速使い始めている。
洗面所で口を下にして、ノズルを口にの中に入れて、歯と歯の間、歯の表面、歯茎に水をジェット噴射する。
私は、歯を磨いた後にフロスをしてから、ジェットウオッシャーを使用するので、それほど汚れは出て来ないが、それでも、たまにフロスで取りきれなかった汚れが落ちてくる。
そして、使い終わった後は、口の中がなんとも言えずとても爽快。
オススメ!
昨日6月1日付け京都新聞朝刊に、木内現会長をはじめとする歴代会長その他の京都弁護士会の賛同会員で、「テロ等準備罪(共謀罪)はいらない!」という意見広告を出しました。
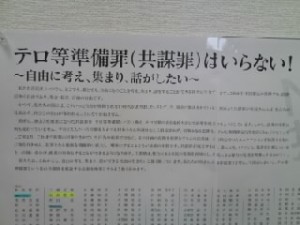
当事務所の村井弁護士は賛同元会長として、私は賛同会員として、名を連ねました。
以下は、意見広告の内容です。
私たち市民は、いつでも、どこでも、誰とでも、自由にものごとを考え、集まり、話をすることができる社会に生きています。これが日本国憲法の保障する、思想・信条の自由であり、集会・結社・言論の自由です。
かつて、私たちの国には、こういった自由が保障されない時代がありました。そして、今、国会に提出されている法案により共謀罪が新設されれば、私たちの社会から、再びこの自由が奪われることになりかねません。
政府は、過去3度廃案になった共謀罪を「テロ等準備罪」と言い換え、テロ対策の名目を持ち出して法案を成立させようとしています。しかし、法案の本質は何も変わっていません。テロリズムという言葉を入れても対象となる集団はなんら限定されず、対象となる犯罪も、テロと無関係な行為を広く含んでいます。そして何より、これまで処罰の対象とされていた行為や結果ではなく、その計画の段階を犯罪とするこの法案は、人の内心やコミュニケーションを処罰するものに他なりません。犯罪となる範囲を飛躍的に拡大し、曖昧にすることこそが法案の本質です。共謀罪が成立すれば、誰にでも、いつでも、犯罪を計画しているという疑いをかけ、捜査の対象とすることができるようになります。共謀罪は、権力による市民の監視を容易にし、市民による権力の監視を困難にするものです。
私たちは、これからも、自由に考え、集まり、話ができる社会に生きたいと強く願っています。私たちの社会に共謀罪は要りません。今国会において、テロ等準備罪という名の共謀罪に新設する法案を廃案とするよう強く求めます。
2017年5月26日金曜日の夜、私が所属する法律家団体が「『子ども食堂』を考えよう」という例会を企画してくれたので、参加した。
場所は、京都市左京区にある「こども食堂のようなファミごはん」改め「あまなつだれでも食堂」。
毎週、金曜日夜、食堂が開かれている。
この食堂は、昨年、子ども食堂のシンポジュウムに参加した時に、パネラーの一人であった林葉月さんが運営者の一人となっている食堂で、シンポジュウムで話を聞いて以来、一度、行ってみたいと思っていた。
場所は、左京区浄土寺の住宅街の民家。「甘夏ハウス」という看板が出ている。


午後7時が集合時間だったが、参加者の弁護士以外に、子ども達や親御さん達で、とてもにぎやかな状況だった。
畳敷きの部屋に、何台かテーブルが置かれ、好きな場所に座る。
壁際には、本日のメニューが並べられているので、好きな量だけ食べてよい。
今日は、ミートスパゲティーと豆腐サラダそしてスープ。
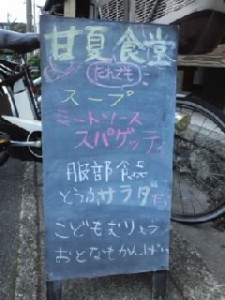
暖かいし、美味しい。
(料理の写真を撮り忘れてしまった・・・)
忙しい合間をぬって、運営者のお一人から、簡単に報告をいただく。
・開始は、2016年2月26日から。毎週金曜日。
・高放射線量地域で暮らす子どもらのための保養合宿で調理を担当されてきた3人で始める。
・食堂の名前を今年4月から変えたのは、「ファミ」が「家族」を連想させること、「こども」だけでなく、幅広い年齢層の人に来てもらいたいから。
・現在は、子どもとその親の来訪が中心。1回に20人から30人が参加。
・食事代は、18歳以下の子どもは無料。おとなは、基本は500円だが、いくら払ってもよい。
・行政にはモノを言いたいから、お金はもらっていない。
・会計は、カンパなどでまかなわれている。
・宣伝方法は、近隣の小学校にちらしを持って行ったりしている。
・経済的貧困だけでなく、「つながりの貧困」もあるのでは。地域の中で夏祭りのようなものも開催していきたい。
「無理しないこと」「続けること」を念頭にされてきたということだが、食材にも良質なものを使用されており、アレルギーへの配慮もある。
利害関係のない関わりやしがらみなく行ける場所が継続的にあることによって、予防的な意味での貧困対策になるのではないかと考え、生きる上でとても大切な「ごはんがおいしく食べられる」場所を提供する。
気負いのない、素晴らしい活動だ。
これからもこのような活動を応援していきたい。
これまで気になっていた品を見つけた時は、なんとなく嬉しいものである。
ゼスト御池に買い物に行き、たまたま見つけた。
それは、FLOAT LEMON TEA
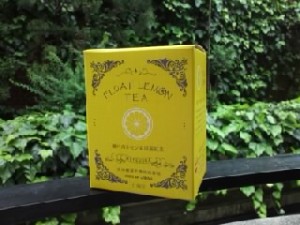
レモンと紅茶のティーパックをセットした新しい形のレモンティー。
以前、料理教室「Angel Kitchen」のブログでAちゃん先生が書かれていて、1度、飲んでみたいと思っていた。
レモンティーは、時々、飲みたくなるが、そのためにレモンを1個買うと使い切れない。
しかし、このフロート・レモン・ティーは、国産のレモンをそのまま輪切りにして乾燥させたものと無農薬・化学肥料なしの国産紅茶のティーパックとがセットされている。

久しぶりのレモンティー・・・
満足、満足