昨年4月1日から10月26日までの約7ヶ月間で、、屋久島の宮之浦岳から北海道の利尻岳まで、自分の足だけで日本百名山を踏破した、アドベンチャーレーサー田中陽希さん。
今度は、今年5月末、北海道の山から始め、日本二百名山を踏破する新たな挑戦を始めている。
(最初の放映は、6月27日21時から。NHKBSプレミアム。)
日本二百名山というのは、百名山の生みの親である深田久弥のファンクラブが選定した山だ。
私もまだ全部は登っていないが、近県で言うと、滋賀県の武奈ヶ岳、三重県の御在所岳など比較的身近な山が二百名山とされている。
でも、北アルプスや南アルプスなどには、2000Mを超える二百名山もある。
本当に人間ワザとは思えないことを、昨年に引き続き、今年もやろうというのだから、すごい。
百名山踏破においても、風邪や足の痛み、そしてかなりの疲労にみまわれていたのに・・・
百名山の時は、日が合わなくて、「追っかけ」が出来なかったが、今度こそ、どこかの山で、田中さんを直接応援したいと思っている。
頑張れ、田中さん!
ブログ マチベンの日々
6月4日、衆議院憲法審査会で、3人の参考人(憲法学者)全員が、集団的自衛権行使を可能とする安全保障関連法案を憲法違反と断じました。
しかも、そのうち、自民党が推薦した参考人である長谷部恭男早稲田大学教授までもが「集団的自衛権の行使が許されるとした点は憲法違反だ」とはっきり述べました。
しかし、菅官房長官は、「全く違憲でないと言う憲法学者もたくさんいる」と居直り発言。
これに対し、「明日の自由を考える若手弁護士の会」(略称 あすわか)がホームページで、早速、「たくさんいる、って?」「たくさんいるなら出てこ~い」などと反論してくれました。
それによると、合憲としている学者は3人、それに対し、違憲を表明している学者は189人でした。
昨日の国会での、辻本民主党議員の「たくさんいるなら、名前をあげて」という質問に対しても、菅官房長官は、3人の名前しかあげられませんでした。
その上で、今度は「数じゃない」と。
いかにこの法案が憲法違反のものか、ますます明らかになっています。
なんということだろう。
マレーシアは、旅客機が行方不明になったり、墜落したりして、大変だと思っていたら、今度は大地震。
6月5日、マレーシアのボルネオ島サバ州で、マグニチュード6の地震が発生し、キナバル山(4095M)に登っていた150名を超える登山者らが被害に遭ったと報道されている。
キナバル山は、東南アジアの最高峰の山で、実は、私は、2001年5月に登った。
私がこれまでに、唯一、海外登山をした山だ。
2000年に世界遺産にも登録されている。
キナバル山は、「海外登山初心者向き」と言われる山で、日本からもたくさんの登山者が訪れている。
1850Mまで車で上がることが出来、そこにゲートがあって、1日の入山者数を制限していると聞いた。
熱帯のため、気候は良い。雪などもちろんない。
登山道は、ひたすら「登り」だが、とても整備されており、途中何カ所も休憩所とトイレがあった。
3200M辺りに山小屋(ベッドやシャワーもある)があり、そこで宿泊し、翌日午前2時頃出発し、4095Mの山頂で日の出を待った。
火山活動でできたキナバル山は、かつて氷河が流れ、独立峰だが、山頂付近はまるでスキー場のゲレンデのように広がる花崗岩の中に、氷河で削られてできた奇怪な岩峰群が林立し、とても幻想的な光景だった。
あの素晴らしい山が、落石や地滑りで、どうなってしまっただろう。
御嶽山に続く、山の災害で、心が痛む。
登山者の無事を祈るばかり・・・
とうとう切り絵に初挑戦!
2015年3月10日のブログでは、「切り絵には、まだ手を出していない(今のところ)」と書いたが、とうとう切り絵に手を出してしまった。
同日のブログで紹介した、切り絵作家の佐川綾野さんが京都に住んでおられること、そして京都で切り絵教室を開かれることを知り、思い切って参加してみた。
時間を間違えて、少し早めに着いてしまったので、佐川さんと少しおしゃべり。
佐川さんは、とても可愛らしい作家さん。
(佐川さん)「切り絵したことありますか?」
(私)「いえ、初めてなんです」
(私)「時間の中で完成するでしょうか?」
(佐川さん)「前のクラスでは、時間内に終わらなかった人もいましたよ・・・」
(私)「・・・」
その日のクラスは、女性ばかり6人。
2度目の参加の方もおられた。
佐川さんの切り絵は、カッターのような刃で紙を切るやり方。
切り方のポイントを簡単に説明受けた後、いざ開始。
作品は、「白雪姫」か「不思議の国のアリス」で、私はアリスを選んだ。
まず、ボードの上に黒い紙を置き、その上に型紙を載せて、テープで固定する。

切りすぎてしまわないよう、おそるおそる、慎重に切っていく。
皆、質問以外には、誰もしゃべらず、黙々と作業に集中する。
切り終えるのに、どのくらい時間がかかっただろうか。
切り終えると、次は色。
佐川さんの切り絵には色があり、その色には、ぼかしのある和紙が使われている。
色及びぼかしを作品のどこに配置するかは、各自の個性にかかっている。
フラワーアレンジでも同じだが、色を自分で選んで配置していくのは大変。
一山超えたら、また一山。
予定時間を少し超えて、どうにか全員完成。
アリスより白雪姫の方が細かい所が多く難しそうだった。
以下は、全員の作品。

そして、これが私の作品。

身体を動かすことも好きだが、集中して何かに打ち込む時間も結構好きだ。
楽しかった!
安倍首相が、5月26日の衆議院本会議で、新たな安全保障関連法案で懸念されている自衛隊員のリスクに関し、「リスクは残る」と明言した(2015年5月27日付け京都新聞朝刊)。
5月20日の党首討論では、自衛隊は「安全が確保されている場所で活動する」と答弁したが、それを軌道修正したのだ。
「国民の命と平和な暮らしを守り抜くため、隊員に負ってもらうものだ」と。
戦後、PKO法などによって、自衛隊は徐々に海外の非戦闘地域に赴くようになったものの、これまでただ一人の死者も出ていない。
自衛隊員は、海外で、平和国家としての象徴として、日の丸のしるしを目立つように身につけ、任務にあたってきた。
それによって、日本の自衛隊が無法に攻撃を受けたことはなかった。
しかし、法案が成立すれば、状況は一変する。
他国軍と「一体となって」「戦闘地域」の含め、活動すれば、相手国から攻撃される危険は高まる。
任務が増大し、あるいは活動範囲が広がれば、「リスクが増大する」のは当然で、そんなことは、子どもでもわかることだろう。
自衛官の家族らの不安は、一層、現実的だ(上記京都新聞)。
夫が海自艦艇隊員の20代女性は、「数ヶ月の任務も訓練が大半だったので連絡が取れなくても安心だった。でも・・・」と言葉を詰まらせる。
「具体的な任務と、それに伴う危険がわからない。わかるように説明してもらわないと、心の整理がつかない」。
元海上自衛隊幹部の坂上隆康さんも「自衛隊は軍隊ではないという言葉遊びは敵には通用しない。海外派遣する以上、戦闘を覚悟しないと」と心配する。
「現場は死傷者が出ることも覚悟している。政治にその覚悟がないなら、部隊を出してはいけない」
この言葉の意味を、政治家はもとより私たち一人ひとりの国民も重く受け止めなければいけない。
いつからだろうか、私が写真を撮られる時には、ほとんどいつもピースサインを出してしまう。
カメラマン氏からは「いつも同じポーズやんか」と言われ、時々、違うポーズに変えてみたりはするが、やはりピースサインをしている時の自分の顔の方が良くて、結局、ピースサインをすることが多い。
京都新聞の連載「時を渡る舟」の「第3部 ピース?」では、5回にわたり、そんなピースサインについて戦後史とからめて紹介されていた。
記事によると、
第2次世界大戦中、反ナチスの象徴として勝利のビクトリーを意味するVサインが欧州で広まった。
英国のチャーチル首相も公式の場で使った。
60年代後半の米国でベトナム戦争への反戦運動や既製の価値観に抵抗するヒッピーたちが「ピース」の象徴に変え、日本に伝わったとされる。
海の向こうで生まれたピースサインが京都の平和運動に流れ着いたのはいつだったのか。
1971(昭和46)年、ベトナム戦争当時、在日米軍基地の米兵と京都の米軍に反対する若者らが1つに固まり、闇に向かってまっすぐに指を2本突き上げていた写真が当時の雑誌にあった。
その後、1995(平成7)年に誕生した「プリクラ」は、反戦運動で広がったとされる「ピースサイン」を日常のものへ、さらにポーズの進化や意味を変容させる役割を担った。
連載の中で、71年「反戦フェスティバル」にも参加した、当時21歳だった京都のシンガーソングライター豊田勇造さん(65歳)が、「今も安易な気持ちでピースはできない」と語っている言葉が強く私の胸に響いた。
折しも、国会では、安保関連法案が審議入りした。
安倍首相は、断定的な口調で「平和な暮らしを守る」と何度も声を張り上げている。
その「平和」は、世界で武力行使をするという意味にほかならない。
私たちは、「ピースサイン」のように、「平和」の意味を変容させては絶対にいけない。
これからピースサインをする時には、思いっきり、戦争のない「平和」を願って、しようと思う。
安倍首相と野党党首による今国会で初の党首討論が、5月20日開かれた。
テレビで時々、国会質疑の中継を観たりするが、なんで、答弁する側は、質問されていることに直截に答えないですまされるのだろうといつも思う。
それが、野党の質問をかわす手法なんだろうか。
ホンネを言ってはいけないからだろうか。
安倍首相は、それが顕著だ。
20日の党首討論もそうだった。
2015年5月21日付け京都新聞は「安保質疑すれ違い」と書いていたが、正にそのとおりで、常日頃、首相が語る「丁寧でわかりやすい説明」とはほど遠いものであった。
例えば、岡田民主党党首が、自衛隊の後方支援に関し、活動範囲が広がれば紛争に巻き込まれるリスクが高まかとただしたことに対し、安倍首相は「安全が確保されているところで活動するのは当然」と答え、正面からの回答を避けた。
また、志位共産党党首の、過去の日本の戦争は間違った戦争だったという認識はあるかという問いに対しても、首相は、歴代の内閣の談話を「全体として受け継ぐ」というだけで、自分の言葉として「間違った戦争」とは一言も言わないのである。
私たちが法廷で尋問をする時、当事者や証人が質問に対し、はぐらかすような答えをすると、裁判官は即座に「聞かれていることに答えなさい」ときつく命じることはしばしばである。
だから、「間違った戦争だったという認識があるか?」と問われたら、その答えは「ある」「ない」「わからない」のどれかであるはずだ。
でも、国会では、このような「はぐらかし」「すれ違い」答弁がしばしば見受けられ、何が国会審議だ、国民を本当に馬鹿にしているといつも思う。
なぜ、首相は一言「過去の戦争は間違いだった、しかし、これからはそのような間違いは絶対に起こさない」と自分の言葉で言わないのだろう。
それは、本音は「間違いだった」と思っていないから、としか考えられない。
将来、日本人が戦争に参加して犠牲者が出ても、また「コントロールされている」はずの原発でもっと被害が出ても、それを決めた政治家は誰も責任をとらない。
そういう政治家を選ぶか否かは、私たち国民自身が決めるということを肝に銘じる必要がある。
2012年3月23日付けブログでも紹介した、タイ料理店「パクチー」。
京都には3店舗あるようだが、私が行くのは専ら河原町丸太町店。
街の屋台風の店で、味も美味しい。
事務所からはやや遠いので、頻繁に行くわけではないが、家裁の帰りなどには、ランチを食べに立ち寄ることもしばしば。
その「パクチー」の店主菊岡美紀さんのことが、2015年5月17日付け京都新聞に掲載されていた。
菊岡さんは、35歳で会社を辞め、単身でタイに語学留学へ。
1年3ヶ月暮らし、帰国後、2009年8月、個人経営で「パクチー」を始めた。
起業したのは、アジアに学校を建てるという夫婦共通の夢をかなえるためとのこと。
2009年創業から丸5年でラオス南部の村に1校目の小学校が完成、3月に開校した。
これも国際貢献の1つの形だね。
これからは、もう少し頻繁に食べに行こう。
先週、京都北山の魚谷山へ行って来た。
「いおだにやま」と読む。
魚谷山の登り口辺りには、ちょうど、クリンソウの群生地があると知り、満開のクリンソウを期待して出かけた。
最初は、ダラダラとした林道を緩やかに登って行く。
川沿いの所々に、ポツポツとクリンソウが咲いていた。
30分くらい林道を歩いた所で、登山道に入る。
登山道に入る所は、川が流れており、丸太の橋がかかっていた。
事故はそこで起こった。
前日の雨のせいか、丸太の橋は濡れていた。
滑りそうで危ないなあと思いつつ、ゆっくり進んで行った。
だが、もうあと1-2歩で対岸に到着するところで、足が滑り、そのまま身体全体が、約2メートルほど下の川に落下した。
身体全体が川の水の中に入り、息が苦しくおぼれるような感じだったので、必死になってもがいて立ち上がった。
身体がフラフラする。
同行者に手を引いてもらい、岸に引き上げてもらった。
背負っていたリュックがクッションがわりになったこと、下が川だったことなどが重なって、幸いにも、ケガは左肘を打った程度の軽傷だった。
ずぶ濡れになったので、上半身だけ着替えた。
しばらく休んで落ち着きを取り戻したので、先に進むことにした。
すぐに、クリンソウの群生地らしき場所があった。
時期が悪かったのか、今年の花のつきが悪いのか、そこにも咲いているクリンソウは所々にしかなかった。
でも、京都の山でもクリンソウが見れるんだなあと嬉しかった。

群生地を過ぎ、柳谷峠を経て、魚谷山山頂(816.2M)へ。
そこで、濡れた衣服を乾かしながら、いつものように焼き肉と焼きそばを作って食べた。
ところで、登山をしていて、転倒することは頻繁にあるが、転落は久しぶりだ。
過去10年で、覚えているのは2回。
1つは、餓鬼岳(長野県)下山中。
木道を歩行している時、滑ってそのまま約1メートル下に落下。下は川だったが、柵があってそれ以上は落下しなかった。
2つは、祖母山(九州)。
急坂の下りでスピードが押さえきれず、そのまま前のブッシュへ落下。
硬いブッシュだったため、それ以上は落下せず、ブッシュの上で、仰向けになって亀のようにもがいていたのを、同行者に引き上げてもらった。
そして、今回。
気を付けないとあかん・・・
昨晩のNHK「クローズアップ現代」は、ガンなどによる1年間の闘病生活を経て、再び「書くこと」を開始され、5月15日93歳を迎える瀬戸内寂聴さんが出演されていた。
お元気そうなお顔を拝見して、とても安心した。
苦しい闘病生活の中で、自分で「痛み」を経験してこそ他人の痛みがわかると語っておられた。
そう言えば、医師の早川一光先生も、これまで何人もの患者さんをみとってきたが、自分がガンになって初めて「死の恐怖」を感じたと言われていた。
そんな瀬戸内さんが、2015年5月10日付け京都新聞朝刊1面の「天眼」という欄に、次のような記事(談話?)を寄せておられた。
それは、50代の女性からの手紙による相談。
一人息子が大学卒業後、就職活動をことごとく失敗し、鬱状態に。
夫も自分も87歳の姑も息をひそめるような暗い日々を送っていた。
ところが、ある日から息子の様子が別人のように明るくなり、自衛隊に入隊したという。
しかし、誰よりも孫を愛していた姑は、「殺される!殺される!」と片手で畳を打ちつづけながら泣いた。
その後、姑は、孫は、やがて戦争にかり出され、戦死するだろうと、ノイローゼになり、寝たきりになってしまった。
格差社会の典型のようなアメリカでは、多くの貧困家庭の若者が兵隊となり、戦地に赴くと何かで読んだことがある。
格差が広がりつつある日本でも、就職できない、あるいは使い捨ての非正規でしか働けない若者が自衛隊に入隊していくのではないだろうか。
折しも、昨日、政府は安保法制を閣議決定した。
憲法の根幹を揺るがすような法案を、アメリカで安倍首相は7月までに成立させると宣言した。
祖母の危惧は現実化してきているのだ。
瀬戸内さんは「彼女の愛孫は、われわれ国民がもっと必死になって力を合わせ、9条を守り抜こうとしない限り、やがて戦争にかり出され、外国人を殺し、自分も外国人に殺されるはめになるであろう」と語る。
私たちが、もっともっと必死になって憲法9条を守らなければならない時が今、来ている。
最近のニュースで、コーヒーや緑茶を1日3~4杯以上飲む人は、そうでない人より、脳や心臓疾患になる率が低いなどと報道していた。
それはともかく、最近、水出し緑茶にはまっている。
テレビで、お茶というものは、本当は水で時間をかけてじっくり出した方が美味しいんだということを知った。
そろそろ冷茶の季節になったので、早速、作ってみようと思った。
そこで、まず、水出し用のポットを購入した。
茶葉用を入れるための網があって、そこに茶葉を入れ、ポットにセットして水を入れておくと、網目から少しずつお茶が抽出されるというしくみ。
濃くなったらひっくり返して、茶葉が水につからないようにすればよい。
そして、茶葉は、有機栽培のものを使用。
何時間、抽出すると、一番美味しくなるかという実験はしていないが、確かに、お茶がとても甘くて美味しい!(私は15時間くらい、おいてます)。

夏のお茶は、これで決まり!
「バイト敬語」と並んで、日常的に気になっている言葉が「ごくろうさま」。
最も違和感を感じた場面は、親が亡くなり、葬儀の準備をしていた時、遅れてやって来た私の身内が、手伝ってくれていたご近所の方に対し、挨拶として「ごくろうさまです」と言った時だった。
「ごくろうさま」は、「お疲れ様」とともに、「ねぎらい」の言葉として使われているようだが、実は「ごくろうさま」は目上の者が目下の者に向かって使う言葉なのだ。
そのようなニュアンスがある言葉なので、たとえ年下の人に対してでも、あまり使いたくない。
「ありがとうございます」「どうもありがとう」でいいんじゃないかな・・・
友人から「日本人の知らない日本語」(著者:蛇蔵&海野凪子)というコミックエッセイを借りて読んでいる。
数年前にはテレビドラマ化もされたらしいが、観ていなかった。
若者言葉がいつのまにか普通の日本語になっていくように、日本語もまた変化していくもの。
その是非はともかく、この漫画を読むと、私たちが、日常、いかに不正確な日本語を使っているかがわかるし、また日本語の起源みたいなものもわかる。
漫画とは言え、勉強になる。いやあ、実に面白い。
中でも「まちがいだらけのバイト敬語」では、私自身、いつも店員さんの言葉に「それ、おかしいんじゃないの!?」って心の中で突っ込んでいたのが、わかりやすく解説されていた。
例えば、
①「ご注文の方(ほう)、以上でよろしかったでしょうか」
②「こちらパスタになります」
③「お飲物は紅茶で大丈夫ですか」
④「お会計、千円からお預かりします」
よく聞きますよね~。
どこが、どう間違っているか、わかりますか?
①「~の方(ほう)」は、「比較」か「ぼかし」の時に使う。
よって、正解は、「ご注文は、以上でよろしいですか?」
②正解は、「パスタでございます」
③「大丈夫」は「問題があるかも知れないが平気か」という時に使う。
よって、正解は、「紅茶でよろしいですか」
④正解は「千円お預かりします」
わかりましたか?
長者ケ岳に登った後は、山梨県の下部温泉に移動。
このブログでも何度も紹介してきたが、「レース切り絵」作家の蒼山日菜さん。
以前に、彼女の「レース切り絵の世界~蒼山日菜と13人の仲間たち~」という企画展が4月4日から「富士川・切り絵の森美術館」で開催されるという案内をもらい、翌日、訪れた。
この「切り絵の森美術館」で常設展示されている蒼山さんの作品を初めて観たのは一昨年のことだった。
その時も初めて彼女の生の作品に触れ感動したが、今回の特別展には、彼女の作品が数多く展示され、1本のハサミでここまで繊細で美しい作品ができるのかとあらためて感動し、十分堪能できた。
また、蒼山さんを師と慕う13名の切り絵作家の作品も素晴らしかった。
蒼山さんの展示会は、6月28日まで。
GWは、静岡県と山梨県の県境に位置する山、長者ケ岳(1335.8M)に登ってきた。
前日に佐野川温泉に泊まり、翌朝、田貫(たぬき)湖畔の休暇村の登山口から登り始める。
登山道はよく整備されており、子ども連れの登山者もたくさん登っている。
林の中のジグザグの登山道を登って行くと、1000Mを超えた辺りに富士山が見える絶景ビューポイントがあり、そこで休憩。
そこから山頂まではやや急坂となる。
今年になってまだ3度目の登山なので、頂上に近づくにつれ、足が重くなり、ストックを支えに身体を上へ押し上げる。
頂上には約20人ほどの登山者でにぎわっていた。
富士山を目の前にして、昼食。至福の時。
やはり富士山は登る山じゃなく、見る山だ。

富士山の雪ももうずいぶん溶けているよう。
下山は、長者ケ岳から約30~40分歩いたところにある天子ガ岳(1330M)を通って白糸の滝方面へ。
300Mくらい急坂を下ると、そこからはなだらかに下っていく。
白糸の滝は、観光客で一杯。

夕方、本栖湖畔でも富士山を撮影。

後からわかったのだが、この位置からの富士山は、千円札の富士山と同じ場所なんだそうだ。
子どもの頃、百人一首のかるたは持っていたが、本来の「かるた」遊びはせず、専ら「坊主めくり」ばかりをしていた。
せっかくそこに、いにしえの「歌」が書かれてあったのに、今から思えば、もったいない話だ。
依頼者の方から、面白い漫画があると言われ、かるたクイーンをめざす女子高生を描いた漫画「ちはやふる」を貸してもらって読んだ。
漫画の方は、現在もまだ連載進行中のようだ。
「ちはやふる」を読んで初めて、「競技かるた」の世界が私の想像を超えたものすごいものであることを知った。
百人一首の普通の遊び方は、上の句を詠んで、それにつながる下の句が書かれた札をたくさん取った方が勝ちというゲームである。
競技かるたは、それとは全く違う。
選手は、25枚ずつ50枚の取り札を幅87㎝の競技線内に自由に並べ、15分間で50枚の位置を暗記する。
読み手は、100枚全部を詠むため、詠まれた札が場にない「空札」もある。
敵陣の札を取ったり相手がお手つきをしたりすれば、自陣から「送り札」ができる。
そして、たくさん取った方が勝ちではなく、自陣の札が早くなくなった方が勝ちという競技だ。
囲碁や将棋のように「集中力」や「精神力」が必要なのはもとより、相手より速く札を取る(というより、はじきとばす)ための「瞬発力」や「体力」も求められる。
その意味で、競技カルタはスポーツかもしれない。
そして、私が何よりも興味を持ったのは、漫画の中に描かれている、名人ともなると最初の一文字を聞いただけで札をはじきとばすことが出来るということである。
すなわち、例えば、読み手が「か~」と詠んだ場合、最初の「か」だけを聞いて、下の句がわかる。
「か」に続く字の音の違いから、同じ「か」でも別の音に聞こえるということらしい。
それを漫画の中では「音になる前の音がある」「音の一歩先がわかる」という表現が使われている。
競技かるたでは、こういう音を聞き分ける能力を「感じ」と言うらしい。
面白いなあと思った。
思えば、中国語でも、「ン」という発音でも「n」と表記されるものと「ng」と表記されるものがあるが、中国人には簡単に聞き分けられるものが、私のような万年中国語初心者にとっては、その違いを聞き取ることはとても困難だ。
そんなのに似ているのかなあ・・・
人間の力というのは、本当に不思議でもあり、偉大でもある。
先週、大学時代の友人と宝塚歌劇を観に行って来た。
私が、最後に宝塚を観たのは、大学時代の「ベルサイユのバラ」以来だから、実にン十年振りの宝塚だった。
私は、関西の人間ではなかったが、西宮に叔母が住んでいたため、「ベルバラ」を観る時までにも小学生の時と高校生の時と2度観に行ったことがあった。
だから今回は4回目。

観たのは、花組の「カリスタの海に抱かれて」とレビュー「ファンタジア」。
トップは、男役が明日海りお、娘役は花乃まりあ。(全然知らん)。
大劇場の1階にはグッズを販売しているコーナーがあり、友人は娘のためと言って、せっせと、他の組のトップスターのグッズを買っていた。
客席はほぼ満席。大半が女性だが、男性もチラホラ。
歌劇の主な構成は、ン十年経っても、全く変わっていなかった。
ラブロマンス、そしてレビューはラインダンスあり、フィナーレは羽つけて・・・と

でも、その時間だけは、現実を忘れ、すっかり宝塚の夢の世界に入り込んでいた。
最近、天候不順が続いているが、暖かくなったので、週末、天気をみはからって午前中だけ近くの山を歩き始めた。
先週12日(日)は、西山へ。
阪急嵐山駅から、京都一周トレイルに入り、まず松尾山へ向かう。
途中、所々に竹藪があり、「竹やたけのこを取るな」という看板がかけてあるのは、まさに西山の雰囲気だ。
松尾山からは、嵐山の眺望が綺麗だった。

松尾山から苔寺方面に下り、途中から沓掛山(415M)へ向かう登山道に入った。
時々、ミツバツツジが鮮やかなピンク色の花を咲かせていた。

沓掛山の頂上で、昼食をとる。いつもの焼き肉と焼きそば。
その後、バスの時間に間に合わせるため、早足で老いの坂のバス停まで下山した。
そして、18日(土)は、大文字山へ。
登り始めると、なんとトレイルランの大会をやっており、上からランナーたちが次から次へと走り下りてくる。
なんとか火床の真ん中まで登ったが、のんびりと登ってられないので、帰ることにした。
鴨川の、わずかに咲き残っているしだれ桜の近くで焼きそばを作って食べる。
偶然、RUN中のF弁護士が通りかかる。昨年末からヘルニアらしいが、10キロは走るという。すごい!
4月11日から13日は、4年に1度開かれる日本医学会総会が京都で開催された。
11日の開会式には皇太子が来たようで、会場の国際会議場に向かう主要道路のアチコチに警察官が立ち、ヘリコプターも長い時間飛んでいた。
4月14日付け京都新聞朝刊で、その総会の学術講演などで、所得や雇用形態によって生じる「健康格差」が大きな課題として取り上げられたことを知った。
データで、15歳時点の家庭の所得水準が低かったという人ほど、高齢期に自立した日常生活を送る能力が低くなりやすいことを説明。
収入の低さと病気の関わりが報告され、社会政策の充実や職場での対策を求める声が上がったとのこと。
現在の日本の所得格差が問題となり、それが日々の生活の格差だけでなく、子どもの教育格差までつながっていることは指摘されているが、実は、身近な健康の格差にもつながっている。
考えれば当たり前だ。
以前、所得が低い家庭の子どもは歯医者にも行けないので虫歯が多いと聞いたことがあるが、所得が低いとがん検診をはじめとする健康診断を受診する割合も少なく、「総じて所得や学歴が低いと健康水準が低い」。
色んな角度から日本社会の貧困格差問題を考えることはとても重要だ。
前もってテーマがわかっていたら参加したのに、残念だった。
4月11日(土)は、午後から、滋賀県に住む友人の書道展に出かけた。
その友人が葉書に書いてくれた「書」を、時々、我が事務所の壁に飾っている。
私は?というと、絵を描くのは好きだが、筆で字を書くのは全く苦手。
子どもの頃、習字を習ったこともない。
だから、書道には全く興味がなかったが、数年前に、その友人の書道展に行き、まるでアートのような作品に触れ、興味を持つようになった。
目の前に琵琶湖が見えるオーガニックレストラン「マドカフェ」でランチした後、書道展が開かれている大津市歴史博物館へ。
篆書(てんしょ)やトンパ文字などで書かれている大きな作品が多数展示され、すごい技やなあと思う作品や、どうやって書いたんだろうと思う作品もいくつかあった。
もうアートそのものや! とても面白い。
友人は2つの作品を出展していた。
友人自身としては、完成度がまだ納得していないということで、2つの作品のうち1つしか撮影許可が下りなかった。
まだ別のコンクールが控えているらしく、「頑張る」とはりきっていた。
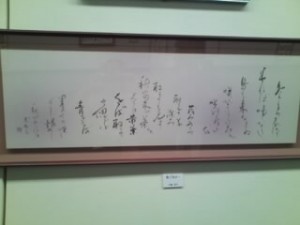
私は、以前「墨絵」に挑戦して挫折しているので、そのことを友人に言うと、「いづみちゃんが墨絵を描いたら、私がそれに字を入れるから、もう1度、やってみたら?」と言ってくれた。
う~嬉しいお言葉・・・